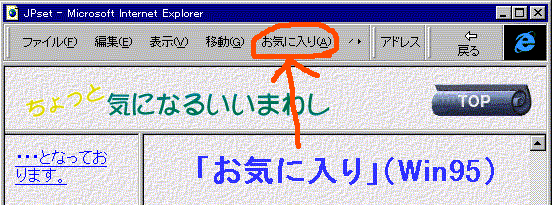・・・となっております。
「2日は休日となっております。」
「飲み物は別料金となっております。」
この言い方で質問者に答える時、具体的に資料を確認するといった行為があれば自然に聞こえるのだが。
「2日は、カレンダー上では休日となっています。」
しかし、直接回答として使用するのは無責任な発言に聞こえる。
→「2日は休日です。」
→「飲み物は別料金です。」
と比べると、発言者の「意志」を感じさせない。既にそうなっている・自分が決めたことではない、というような責任回避的響きがあってなんとなく不快になる。
(99.5.7)
- <後日付記>
-
2000.5.24付の新聞によれば「ぼかし言葉」が広がっているという。
例として挙げられているのは
-
「お荷物のほう、お持ちいたしましょうか?」
「とても良かった、みたいな・・・」等。
-
断定を避け、責任回避を計る心理と理由付けされている。
断定を避けて口調を和らげるのは日本語の語感として別に奇異ではない。
私が気になるのは業務上の回答等、きっちりと明言しなければならない場面でも、機械的にこの「ぼかし言葉」を使おうとする傾向があることだ。
-
○ついでにもうひとつ気になるこの「営業用ぼかし言葉」を上げておく。
-
電話で自分の名を伝え、「失礼ですが?」と言ってそのまま答えを待つ。
-
「失礼ですが、お名前をお聞かせ願いますか?」の後半を省略したものと推測はつくのだが。
本当に失礼だよ!これは。
-
「お名前を頂戴できますか?」というのもある。
-
よせやい、名刺だったらあげないこともないんだが。人の名前をもらってどうするんだ?
明日からその頂戴した名前で立派に生きていく覚悟なんだろなぁ?
-
(00.5.25)
- <更に付記>
-
-
上記の記事を書いてから久しいが、「となっております」の横行はいよいよ目に余る。
当初は若い女性の話し言葉の中だけだったのだが、最近ではとうとう書かれた文章にもこれが見られるようになってきた。
いろいろあるのだが、やり玉にあげる相手として南禅寺サンを名指しさせてもらう。
-
.jpg) (京都 南禅寺山内掲示)
(京都 南禅寺山内掲示)
-
↑尻がむずむずするような落ち着きのない日本語である。
-
さすがに「となっております」ではなく、より書き言葉に近い「になっています」となっているが、軟弱な精神構造は変らない。
-
この日本語がおかしく感じるのは、禁止になっている根拠が明示されていないと感じるからだ。
この文の提示者の意思ではなく、他の根拠から既にそうなっているので、という口調に聞こえる。
「何故禁止なんですか?」と問い詰めれば「さあ?私が決めたわけではないので・・・」という逃げ口上がすらすら出てくるような心理が透けて見えている。もうすこし座禅修行し、書き手の主体性が感じられる文章をものする精神になって欲しい。
- 「当山の業務遂行要領では、室内の撮影は禁止になっています。」なら、精神の軟弱は感じるが日本語がヘンとは感じない。
根拠を示さないのなら「室内の撮影は禁止します。」にし、提示した当事者の意思を明確にしなければならない。
- こんな軟弱な文に守られて室内の虎も悲嘆の念にくれているのだが、その姿を見せることはなぜか禁止になっているのである。
(07.01.17)
・・・させていただきました。
「この会に参加させていただき、みなさんとごいっしょさせていただき・・・」
余計なことなんですが、自分としては本来してはいけないとは分ってるんですが、人からいろいろお誘いをうけたりして、もうことわりきれないので、不本意ながらこうしてしまいました、悪いけどごめんなさい、というようなニュアンスがある。
しかし、別に悪いことでもないのにそーいわれると、丁寧すぎていらいらする。
自分の行動に自信が無いのでとにかくあやまっておこう、というような事勿れ主義にうんざりするからか。
→「この会に参加し、皆さんと御一緒できて・・・」
本来は自分の意志ではないのにしてしまいました、というニュアンスは謙虚に聞こえるので愛用する人は重宝して手放せなくなるようである。
「長年の間市政にたずさわらせていただき、もっと皆様のお役に立たせていただきたいと、このたびの選挙に立たせていただきました。」
この、あまりの主体性のなさ。立候補くらい自分の意志でしろよ!
(99.5.7 00.5.25多少修正)
おつかれさまです
ごくろうさまです
どこかの新人社員研修では「ご苦労さま」は目上の人にはつかえないと指導しているらしい。
◎「ご苦労様はねぎらいであって、目下が目上をねぎらえない」とのこと。
しかし、日常感覚では普通に使用して一向に失礼でない。むしろ、相手が職務上の行動をとっている時には、普通に「ごくろうさまです」と返すような気がする。黒猫ヤマトのお兄さんに「ごくろうさまです」といっても目下だからという意識があるとは思えない。
◎件の研修マニュアルでは「ご苦労さま」の代わりに「お疲れさま」の使用がよいとされているらしい。
「お疲れさま」もねぎらいのようにきこえるんですけど?どー違うんでしょうね。
むしろ目下から「ご苦労さまです。」といわれて心証を害する感覚の方が、なにか尊大でうっとおしい気がする。
(99.5.7)
「責任」
自動車学校の学科教本に「運転者の責任」というのがあった。
1.刑事上の責任
刑務所収監・実刑に服する
2.民事上の責任
損害賠償・補償
3.司法上の責任
免許停止・剥奪
(4.倫理責任)
という風になっている。上記の例はすべて安全な運転をするという責任を果たさなかった結果の罰則のことで、責任の分類にはなっていない。
責任という言葉の意味が「罰」と混同されている印象がある。
責任はResponsibilityの明治の訳語と思うけど、英語の用法ではどうか。
例えば)
The NATO alliance offered Sunday to assume responsibility
for the hundreds of thousands of Kosovo refugees.(NY times '99/4/15)
(コソボ難民にたいする責任を果たす)
果たす目的語は「罰」ではいけないとおもうがなぁ。
(99.5.13)
自動車免許証○×学科試験問題
ふと魔がさして自動車教習所に通うハメになりました。
学科教科書の↑の文章もひっかかりましたが、他に学科試験と称して○×をつけさせられる問題にはおかしなモノが多いようです。
ちなみに、上記の「責任」に関する問題は:
□
免許証を手にするということは、単に車が運転できるということだけではなく、同時に刑事、行政、民事責任など、社会的責任が重くなることを自覚しなければならない。
→「社会的責任が重くなる」という表現はなんとなくわかるけれど、「行政責任」が重くなるというのは大袈裟で何かおかしい。よせやい、別に当方は政治家でも官僚でも何でもないただの安サラリーマンだぞ!と返したくなる。「行政責任」の内容は単に「免許を取り上げられる」ということらしい。こういう文章に対して○をつけなければならないハメになった自分が悲しい。
□
自動車を運転している以上、沿道の人々に対して騒音、振動など迷惑をかけることはしかたがない。
→模範解答は×。しかし、どんなに注意して運転しても排気ガスは出るし、エンジンは振動するし、沿道住民に迷惑になることは事実である。これを「しかたがない」と思わないのが正しい態度ならば、「迷惑をかけるのは運転者の権利である」とでも思ったらいいの?
□
集団で走行する場合、並進して、他の車に迷惑にならないようにする。
→日本語があいまい。「並進して」の位置に「安全運転をして」を入れても、「無謀な運転をして」を入れても読めてしまう。この読点の打ち方だと「並進せよ」という文章に見える。
しかし、模範解答は○。日本語が悪いと抗議したところ、採点の指導員氏と険悪なことになってしまった。
□
車を運転して集団で走行する場合、ジグザグ運転や巻き込み運転など他の車に危険を生じさせたり迷惑をおよぼすような行為をしてはならない。
→こんなことはしてはいけません。答えは○。でも、これは「集団で走行する場合」だけでしょうか。集団でない場合はジグザグ運転をしてもいいのでしょうか?良く考えると×にしたくなってくる問題。
□
二輪車を運転するときは、短い距離でも、げたやサンダルなどの運転の妨げになるはきものをはいて運転してはならないが、半そでシャツや半ズボンなどの軽装で運転するのはよい。
→模範解答は×。しかし、この「よい」という言葉が非常にあいまい。別に道交法では服装の規定はしていないのだから、半ズボンで運転してもよい、○ではないか。
全般に「法律(道路交通法)上許される」という「よい」と、一般的注意としての「よい」が区別なく出てきてまぎらわしい。
(以上文例は主として「問題の学習」(c)中部日本自動車学校発行・編集より引用させていただきました。)
(99.5.20)
(特別付録)運転免許試験学科問題パロディ
あまりにばかばかしいので、腹いせに作ったパロディでございます。
○×でお答えください。
○コカインを吸入したので車を運転しないようにした。
→道交法上は○です。他の法律上は知りません。
○地下街等歩行者の多いところを通行する時は必ず徐行しなければならない。
→多分地下街は歩道扱いでしょうけど。
○逃走中に後ろからパトカーが追いかけてきたが、交差点・その他の近くではなかったので、道路の左側により、一時停止はせずそのまま逃走を続けた。
→道交法上は○です。安全運転に気を付けて正しく逃げてらっしゃいます。
○体重が150キロを越える人は危難なので原動機付き自転車には乗らない方がよい。
→道交法上の規定はありません。もっともだと思えば○、余計なお世話と思う人は×をつけてください。
○2輪自動車を手で押して通行中でも、エンジンを切っていなければ歩行者とはみなされないので、時速60キロを越えて押してはいけない。
→正しい。あまりに正しい。
○道路上で二台の車でつな引きをするとき、一台の車の総重量が750kgを越える時はもう一方の車の運転にはけん引免許が必要である。
→さあ?必要なのと違う?
○運転中の性交はいけないが、フェラチオならばしてもらってもよい。
→この問題の回答は尋ねた人全員が○と答えました。
それから、試験問題の漢字には必ずルビが振ってあるのは何故なんだろうか?
もしかして、漢字を習ってない小学生でも試験を受けられるようにという配慮?
ある程度の漢字が読めないと、道路標識なんかも分からないと思うけどなぁ。
(99.5.20)
「お気に入り」(Win95)
昨年米独禁法違反で訴えられていた、Win95押し付けWWWブラウザ「インターネット・エクスプローラ」の
book mark フォルダに勝手に付けられているフオルダ名。
www検索にとどまらず、windows標準のファイルオープン・ダイアログボックスを開くと「お気に入り」フォルダに直接飛ぶボタンがついている。
正式フォルダ名は英語「favorites」としてシステムフォルダ内にある。
なるほど、英和辞書には favorite
の名詞訳語として真っ先に「お気に入り」とある。
ちゃんと訳語はあってる。しかし、私はそれが「気に入らない」。
当方の語感では「お気に入り」は女性ことばであって、気恥ずかしくて使えない。
例)
favorite book は「お気に入りの本」ではなくて「愛読書」
favorite horse は「お気に入りの馬」ではなくて「本命」
favorite shop は「お気に入りの店」ではなくて「ひいきの店」、せいぜい「気に入ってる店」
ま、試しに「スタートボタン」をクリックしてみませんか?
するすると出てくるメニュー表示を見てください。
気持ち悪くないんでしょうかね?
言葉のレベルを揃えて「よく使用するファイル」とかにすべきですよ。
最初、ツールバーに並んでいるこの言葉を見つけたとき、なんて安直な訳語だと思った。しかし、直ぐもっとマシなニュートラルな名前に差し替えられるだろう、とも思ってたのだ。しかし、甘かった。当方が抗議の声をあげるのを怠って4年。この、なんとも収まりの悪い、きもちわるーい名前は居座ったままで、返ってシステムのデフォルト・フォルダ名として定着したような落ち着きぶりである。いかん。今からでは遅いが、とにかく「気に入らない」と抗議の声をあげておくぞ。
(99.9.10)
カタカナ語
これはよくあるアルファベット起源カタカナ語。いちいち
書いてるとキリがないけど。ま、特に注意を喚起するというイミでリストアップします。
表記が気になるモノ
デジタル
- この言葉ははっきり覚えてる。20年前「デジタル時計」で急に一般的になった。
英語の綴字は"digital"。ま、もともとカタカナ表記は無理があるので近似値となるのはやむを得ない。
しかし、ディーゼルとかディクショナリという表記もあるのだから「ディジタル」となるのが当然と思ってたのに。
「ディスク」/「デスク」の類かな。
はっきりいって「デジタル」は臭いからイヤだよ。
アドバイサー/ヘットホン/ベット
- 確かに英語の語尾の子音の発音を聞き取るのは難しいし、なんとなく意味はわかるんですけど。
でも聞いて気持ち悪い。いや、別に悪気で言ってるんじゃなくてホントに背中がもぞ痒くなるくらい気味が悪いんです。
だから "adviser" "Headphone" "Bed" は 「アドバイザ/ヘッドフォン/ベッド」って言ってください!
ヒラにお願い申し上げます m(__)m
あ、巨人の長島サンも「スピート」とよくいってたなぁ。
(00・6・12 ちょっと修正追加)
シュミレーター
- ひところはこう書く人もかなり多かった。
最近は割かし正しく「シミュレーター」になっているようだ。
略しすぎ
ビデオ
- 日常的には聞きなれているけど、「当社のビデオをお買い上げ下さってありがとうございました。」という文章を見るとイヤな気分になる。
話し言葉として使っているときは「ビデオ・テープ」もくしは「ビデオ・テープ・プレイヤー」の短縮語として意識しているが、文章にするときは省略してしまうと、なにかおかしい。
しかし、まてよ。この文章の作者はビデオ・テープ録画再生装置のことを英語でvideoというと信じているフシもあるよーな。うう、おそろしー。
同類:テレビ、レコード
アパート/デパート/スーパー/コンビニ
- いちいち解説はしませんが。英語を喋らなくてはならなくなった時、ついまちがえそう。
モツレク
- これはモーツアルトのレクイエムのことだそう。
私は絶対に口にしたくない。←問答無用。面白くとも何ともない。ただ下品なだけ。
一種の業界隠語的な使われ方がされていて、「モツレク」って何?というような顔をすると「このド・シロートめ」というような反応があるのもうっとおしい。
もし仮にアンタがプロだったとしても、どのみちアンタの音楽はそのレベルだよ。
ミッション/オートマ
- 最近自動車学校に行って初めてこの世界の用語を教わった。
「ミッション車」というコトバを聞いたとき、キリスト教の伝導に使う車かな、と一瞬思ったりした。
「ミッション」というカタカナが車のマニュアル・トランスミッションというイミで最初に入ってきていたら違和感はなかったのかもしれないけど、この年齢になって初めてこの用例を聞かされたらびっくりするよ。
「オートマ」? なんでこんな中途半端な略し方をするの?
あ、「オート」にすると親分格の「オートモービル」と混同するからか!
そこまで苦労するんだったら素直に「オートマッチク(・トランスミッション)」といったらいいのに。
インフレ/デフレ
- こういう用語になるとあんまり違和感がない。なんでかな。
この省略法で混同することもないし、最初からただひとつのイミで通用しているし。
ネゴ/コンペ
- しかし、このカタカナには違和感がある。ネゴシエーション/コンペティション以外には考えられないので混同はしないんだけど。
語感が汚い。それしかない。
オリジナルとイミが違うもの
コンセント
- 英語の辞書を見ても電気の差込プラグというようなイミはない。
実は日本産業黎明期にさるメーカーが電気の差込(プラグ)を売り出すとき銘々した商品名が「コンセント・プラグ」だったそうだ。
で、例によってケチくさく省略されてしまい、最後に「コンセント」が日本では差込プラグという普通名詞にめでたく出世した感動の物語。
なんか、やばい日本語だけど、素直にエライとも思うね。
ちなみに普通名詞並の地位を獲得した商品名を挙げると:
ジープ
うどんすき (最近「美々卯」以外でも普通名詞として使用しても可との判決が出た)
セロテープ
味の素(あ、これは「化学調味料一般」という意味では最近見ないか)
- フランス語にもこの手のものがある。
Bicはボールペンメーカーの商標だけど、かなり「ボールペン一般」という普通名詞として使用されている。Walk-Man
もね。
多義のオリジナルの一義しか使わないもの
(ま、ほとんどのカタカナ語はそうなると思うけど・・・)
コマーシャル
- このカタカナ語はほとんど「広告放送」という意味だけで使われている。
本来の形容詞「商業の」というときには使用されていない。
エンゲージ/プロポーズ
クレーム
- 「異議申立て」のようなカタカナ語感があるが、英語claimとはかなりズレている。
Does anyone claim this watch? 「この時計誰の?」(自分のものとして要求する)
イメージ
- 「この写真はイメージです」
と先日買ったお菓子の袋に印刷されていた。
「イメージ=想像(図)」という直線的置き換えだろうけど、唖然といたしました。ま、なんというか写真は必ずイメージなんだけどなぁ。
最近のパソコン(うっ!カタカナ語・・)の世界では「イメージデータ」とかいうような用例も多い。これは「画像データ」。
だから文頭の引用は「この写真は画像です」という意味を最初に見てしまう。子供向きのお菓子なだけに、そう断らなければ
写真を食べてしまうガキもいるのではないか、という意味の注意書きなの?これは。
品詞の用例がずれているもの
アバウト
- 「アバウトでいうと」
この用例なんか聞いていると、「about=だいたい、おおよそ」という知識だけがあって、単純に日本語を英語らしきカタカナ語で置き換えているだけですね。
品詞もなにも考慮 されてない。
それで「おおよそでいうと」とどう違うかというと、イミ的には何も変わっていない。
ただカタカナ語を入れるとかっこいい、というような意識だけ。
日本語も英語も悪くなるだけだから、こんな言いかたはやめようよ。
(99.9.10)
ローマ字表記の名前と欧米人呼称法
”Ichiro SUZUKI” と 名-姓で書くこと
日本人名をローマ字表記にするとき習慣的に「名-姓」の順で表記していたが、これを改め「姓-名」の順で表記したいとの国語審議会の提案があったという。(朝日新聞天声人語 2000/6/10付)
確かに子供の頃ローマ字で名を書くとき Ichiro SUZUKI というように姓名をひっくり返すような書き方をしていた覚えがある。
いまでは恥ずかしくてとてもそんなことはできない。
別に欧米人に見せるためだけにローマ字表記を使用している訳ではないし、また欧米人に示すにしても別に"SUZUKI
Ichiro"と日本式順序で表記しても一向にかまわないのである。
ローマ字表記姓名の習慣的語順「名-姓」に関して、上記天声人語氏は『欧米が自国流の「名−姓」を押しつけたのではなく、こちらが申し出た形である。』と書いている。
つまり、要求されてもいないのに親切めかして行われる過剰サービスですね。あなたはわたしの国の習慣は何も知らないでしょうから、あなたの国の習慣にあわせて自分の名前をアレンジして書いてあげましょう、という訳だ。
そのくせ別に日本在住の欧米人が「クリントン・ビル」風に日本の習慣に合わせて語順を変えることは期待してないようである。
だから過剰サービスという以外にはないんだけど。でも、それだけではないと思う。
昭和30年代にフランク永井という歌手がいた。別に在日2世であったわけではなく、単なる芸名である。これが「名-姓」風芸名のはしりだと思われる。
この芸名の由来はよくは知らないけど、もちろんインターナショナルな歌手を目指したというわけではなかろう。
このカタカナ交じりの「名-姓」順芸名に対し、なんとなく「バタ臭い、ハイカラな、イキな、都会風な」というような感じをうけたのが当時の一般的感性ではなかったか。
高度経済成長期前の一般日本人が「名-姓」順のローマ字表記で自分の名前を綴ったとして、彼等がすべて欧米人に実際に会って自己紹介する時のことなんて考えていたとは思えないのだ。
ローマ字で、そして「名-姓」順表記をすることで何となく自分が欧米人風になったようで、「かっこいい」と感じた人が多かったというのが真相ではないかと思う。
私の場合、数年にわたるヨーロッパ滞在中も含み、もう20年来「姓-名」の順で表記しているが別に不都合はないし、もしどこかで不都合があったとしても「名-姓」表記する気恥ずかしさには耐えられない。それどころか、最近では他人サマが
Seiji OZAWAとか表記されているのを見ただけで他人事ながら気恥ずかしくなってしまう過剰羞恥心も出てきてしまった。
やめなよ、それ、「名-姓」順にしても別にかっこよくともなんともないよ。
もちろん、欧米人とのコミュニケーション中や、英文中で姓と名を明示するためならアリですよ。
(00.6.12)
- (追記)
-
(2000.9/8付毎日新聞より引用)----------
今後の国語施策のあり方を検討している文相の諮問機関「国語審議会」は8日、総会を開き、日本人の姓名のローマ字表記を「姓―名」の順にすることが望ましいとする委員会案を公表した。これまでの慣行では、欧米人と同じ「名―姓」表記が一般的だが、文化の多様性を考えた場合「日本の形式」で通すことがよいとしており、今後議論を呼びそうだ。
-----------------------------------------
日本人がどうして名・姓というバタ臭いローマ字での署名順序を採用したかについては単に鹿鳴館的盲目的西欧追従がなせるワザと思っていた。
最近、すこし違った理由もあるような気がしてきた。
日本人の場合、中国人、朝鮮人のケースと比べて姓に対する執着がそんなにないのではないか、というのも理由のひとつだと思える。そういえばこの2国は夫婦別姓が一般的な国である。
江戸時代以前には人口の大多数は姓を持たなかったし、苗字持ちも「木下・羽柴・豊臣」風に簡単に姓を変えていたようである。
山田とか横山とか聞くと、明治になって急に苗字を名乗れといわれたとき、かなりいいかげんにでっちあげたような印象がある。山に田んぼというのはかなり一般的な日本の光景ではないだろうか。「苗字なんて何でもいいよ、めんどくさいから山田にしとこう。」くらいのノリを感じてしまう。名前だって長男だから「一男」でいいじゃんという軽いノリ。そういえば昔「山田一男」さんという指揮者がいたっけ。え?今も居る?すんません。
中国や朝鮮では姓は出自を示す重要な個人指標であった。
韓国には本貫同姓(同じ出身地の同姓者)同士は結婚できないというような慣習があって時として悲恋非劇を生んだという話もよく聞いた。
日本ではそれほど出自にはこだわらなかったということになるのかな?
だから別に欧米風に「名ー姓」だってかまわんのでは?という気分があったような。
それにしても、いつ誰がローマ字表記の署名で「名・姓」方式をはじめたのだろう。
初めて欧米との外交文書に署名した明治の日本外交官がローマ字でどのように署名していたんだろう。ひょっとすると誰が最初にこの尻の軽い「名ー姓」署名を始めたのか特定できるかもしれない。
(00.9.20)
外国人に対する名前の呼称
私の同僚に「山本エミリ」さん(仮名)がいる。米国籍だけど、山本氏と結婚したので「山本エミリ」と名乗っている。
この人は会社では「エミリさん」としか呼ばれたことがなかったようだ。
これは2重どころか3重くらいにおかしい。その「おかしい」という感覚が「エミリさん」と呼ぶ人と共有できないので何時も困ってしまう。
先ず、日本の姓名呼称の習慣では会社のようなオトナの社会では「名前」ではなく「姓」を呼び合うのが普通である。現に日本人同士だったらちゃんと「姓」+敬称で呼び合っている。
どうして外国籍であっても社員同士なのに「姓」を呼称しないんだろう?
欧米では職場で「名前」を呼び合うこともある。むしろ下級雇用者同士だと「名前」を呼び合う方が普通かもしれない。その意味で「エミリさん」と呼びかけている人は、欧米式呼称方を過剰サービス風に採用しているのかもしれない。
しかし逆に「エミリさん」から、姓ではなくて自分の名前を呼ばれたいと思っているというわけではなさそうである。自分は相手の名前を呼ぶけど、相手が自分の名前を呼ぶのは許さない一方通行の勝手な呼称システムである。
第一、相互に名前を呼び合う呼称体系だとすると「エミリ」「キヨタカ」風に敬称抜きで呼び合うことになるハズで「エミリさん」と敬称をつけているのはちとおかしい。
結局これも日本の習慣とか欧米流とかまったく関係が無くて、ただ単に外見容貌が欧米人である婦人を日本の姓「山本さん」と呼びかけるのに違和感があるということだけではないか、と思える。いってみれば「ガイジンはガイジンらしくないと」という気分である。
そういえば、どうして「山本さん」と呼ばないの?と訊ねると、件の「エミリさん」呼称者の返答は「だって、エミリさんはガイジンだし」ということでありました。
これは困ったもんだ。こういうのを差別というんだけどなぁ。多分本人は差別しているという意識はないんだろうなぁ。
(00.6.12)
- (追記)
- サダム・フセイン イラク元大統領の死刑が執行された。(06.12.30) これを報じるNHKのニュースでは「フセイン元大統領」という呼称を終始使用していた。
姓名基準はイスラム圏では又違ったシステムが行われている。このサダムの次のフセインは父親の個人名である。姓ではない。だから「フセイン元大統領」という呼称では誰も示していないことになる。
これを西欧式に「姓(family name)」と単純に決め付け、使用し続けたNHKはじめ日本のマスコミ各社の不見識と、イスラム圏文化軽視は容認しがたい。「サダム・フセイン大統領」とどうして正しく報道できないのか?
- ちなみに、欧米のマスコミでは圧倒的に「Saddam」とのみ呼称するケースが多く、「(former)
President Hussein」は少なかった。
日本のテレビで見た中では一人、中東問題の専門家だけが終始「サダムは・・」と呼称していたのが印象的だった。
(07.1.17)
負けないようにがんばります
こども大阪府議会という催しをテレビのローカルニュースで見た。
府下の小学生が府議会場で議会の擬似体験をするというもので、このときの議案で可決されたのは「たこやきを大阪名物として振興しよう」ということである。
終了後の参加小学生のインタビューで一人がこう答えていた。
「他の小学校からのみんなもがんばってるので、ぼくもみんなに負けないようによい意見を出してがんばります。」
うむ。そんなにがんばらなくてもいいと思うがなぁ。
ぼく達は「他のみんなに負けないようにがんばれ」といわれて育ってきた。
「勝て」とはいわれなかった。ただ他のみんなと比べたとき「恥ずかしくないように」がんばるのだ。だから勉強してそこそこの大学に入り、そこそこの会社に勤めてそこそこの生活をする。別に勝ちはしないけど、みんなに負けないようにがんばったのだ。
もちろん勝たなきゃイミがないという人がいて、そういう積極的な姿勢がその人にとって非常にいい結果を生み出している場合も多いと思う。
しかし、「負けないように」というのはそういうことではない。
「負けないように」というのは勝つということではなく、他人と同じレベルでいようという集団帰属意識をいっているように思える。他人に遅れをとらないように、常に同じレベルで生きていこうといっているのだ。
結局ぼく達は自分の生きかたを他人との比較で決めてきたようなのだ。
自分自身を絶えず他人と比較し「負けないようにがんばって」しまうつらい習性。
「みんなでがんばろう」
「みんなでがんばりましょう」というのも同じような集団帰属意識が働いている。
今日もオリンピックの勝者がインタビューで「この勝利はみなさんのおかげです。みんなでがんばったので勝てたのだと思います。だからこのメダルはみんなでもらったものです。」といっている。
別に「オレが世界一だ。このメダルはオレの実力だけで勝ち取ったんだ。ざまー見ろ、文句あるか。」と言ってもいいと思うのに、絶対にそれはない。
敗れた人はどいういかといえば「せっかく皆さんが応援してくれたのに、自分の努力が足りず、負けてしまって申し訳ありません」と謝っている。
論理的にいうならば「私が敗れたのはみなさんのおかげです。この敗戦の責任は私個人ではなくてみんなで負ってください。」でないと、先の勝利者の発言とはつりあわないと思うが。
まあ、でも基本的には個人を全面的に出さず、なにごとも集団単位の行動様式に個人を合わせていくという生きかたは無難で謙虚でぼく達の大多数に合っていると思う。
ただ、気質や感じ方が違うので、どうしても自分の所属集団にあわせることができない人もいる。こうした少数の人にとって集団主義が基本原理である社会で生きていくのはとてもしんどいことである。
去年所属していた合唱団を辞めたのも「みんなでがんばりましょう」という風潮に話をあわせるのがどこかしんどかったこともある。別にそんなにがんばらなくってもいいんじゃないの?と言えない雰囲気がある。
がんばりたい人はどうか、がんばって下さい、私はパスしたいんですが、なんていうと、「みんなでがんばるから意味があるんです!」といわれてしまうような。
自分にあった身過ぎ世過ぎの方法があるはずだ。他人との比較、仲間との共同というような他人との関わりにおいてだけ自分の行動を判断するのではない、何か別の。
「とにかくがんばれ」
「がんばれ」という言葉は欧米言語に翻訳不能であるというのはよく言われる。
個別に「勇気を持て」とか「戦う精神」とか状況にあわせて訳さねばならず、日本語の「がんばれ」の万能振りにはかなわない。
例えばスポーツをする人に「がんばれ」というのはちゃんと訳せると思う。
もっとも、私ならスポーツ選手への声援だとしたら「がんばれ!」は”take
it easy!"「気楽にいこう!」と訳すつもりですが。
しかし、人と別れるときに挨拶がわりに使う「じゃ、ま、とにかく、がんばってね」という無目的的用法は訳しようもない。強いて言えば「生活」という目的語を補って「がんばって生活するよーに」といってる風である。
欧米語の語感からいうと「生活」が呼び出す動詞は多分「楽しむ」くらいではないだろうか。"enjoy
your life"というように。
日本語「がんばる」からは努力主義の色合いが濃く透けて見える。
本当は何らかの目的を達成するために「努力する」んだけど、目的が達成できないときには「努力する」ということ自体が採点評価基準になる、というのが「努力主義」である。
「結果は良くなかったけれど、がんばったんだからいいか。」というヤツですね。
結局、勝ち負けタイプの体育会系生き方では必然的に敗者になる人も出てくる。しかし、敗者になったとしても、とにかく「がんばった」のだから良しとしよう、という救済措置がこの努力主義というわけだ。
だからこの「とにかくがんばる」無目的的がんばりモードは敗者でさえそれなりに満足できる、それなりに有効な、かなり完成されたシステムということができる。
だから、スポーツのような勝敗がはっきりしているものだけでなく、結果も出ないような生活全般や社会との雑多な関わり方なんかにも「がんばって」しまうヒトも多い。かくて別にそんなに力を入れる必要もないところにまで「とにかくがんばる」心理も働く。
昔山陰の方にスキーバスで出かけたら、途中現地の雪の状態についてのアナウンスがあった。
「今現地ではたくさん雪が降っているという連絡がありました。皆さん、存分にお遊びください。」車内では思わず歓声が湧きあがった。ぼくもうれしかった。
今までマイクのようなものを通じて公式に「お遊びください」なんていわれた事がなかった。
「しっかり勉強してください」だの「がんばってください」だのばかりだった気がする。
もちろん私的にはサボったり、手を抜いたり、あそんだりしてきたのだけれど、何か公式な場では「おもいっきり遊んでください」という風なことをいわれたことがなかったような気がする。
小学校の時に遠足といってたものが中学校では「校外学習」という名になっていた。娯楽で旅行するんではない。何かを学ぶために行くのだ、というような意気込みか。
全てに「がんばる」という姿勢を良しとする風潮が感じられる。
がんばること。結果はどうであれ、無目的的にがんばること。
「死ぬ瞬間」シリーズの著者、キューブラ・ロスのいうところによれば、死の床にある病人に見舞いの人や家族が「死んではだめ、がんばって早く良くなって」というように励ますのが良くないそうだ。
本当は安らかに死んでいけるのに、周りの人が無責任に励ますので死ぬことが非常な苦しみになるという。
もうぼくはいいよ。
もう何事もがんばってしたくはない。
お願いだから「べつにがんばらなくてもいいよ、楽に行こうよ」といって欲しい。
(00.9.22)
再生紙の使用
「この紙は再生紙を使用しています」(大和郡山市広報誌等)
その1)
別に言い回しが変だというわけではないが、どこか割り切れない変な感じがする。
どんな紙を使用していただいてもいいんですが、私は別に紙の材質に興味があって見ているわけではない。見る人にとってまったく必要のない情報ですね。
出会った人にいきなり「実は私は合唱をやってまして」と唐突に話し掛けられたような気がして困ってしまう。別にそんなこと聞きたいわけではないんだけどなぁ。
この場合正直に「それがどうした」と返せば気まづくなるので、「はあ、へ〜え、そうなんですか?」といかにも感心したといように答えないといけないとつい思ってしまう。ここでは、「天然パルプ材の資源保護を心がけていらっしゃるんですね」と答えるのが礼儀というものである。
しかし、なんか変だなぁ、と思ってしまうのは、どこか「吸わないほうがいい」と表示しながらタバコを売っているタバコメーカーの矛盾と通じるものがある気がするからだ。
再生紙使用という表示なら100%の古紙を使っているのではなく、新たなパルプ材をつぶした新紙も混入しているのである。*1)
資源の保護をいうなら、こういった印刷物自体を廃止するに越したことはない。ま、すべての印刷物を廃止するワケにもいかないでしょうが、不要なページの削減や発行回数部数を抑える等の総合的な取り組みの一環として「再生紙の使用」があるべきです。「再生紙使用」この表示さえ入れておけば事なれりというワケではない。
官製年賀状に「再生紙使用はがき」と印字するくらいなら、いっそ「資源保護のため年賀状の出しすぎに注意しましょう」と印字しておけばいいのではないか?
(00.12.22 02.3.3大幅改訂)
- 後日注記*1)
- 「再生紙使用」の場合多くは古紙使用率70%、100%古紙使用なら「この取扱説明書は、古紙配合率100%、白色度70%の再生紙を使用しています。」のように明示することになっているそうです。(2002.3.3 Thanks to mr.Yabuki@seibunsha )
その2)
ずっと再生紙ってゆーのは、あのワラゴミみたいな繊維カスが浮き出た、ざらざらごわごわの茶色の紙だと思ってた。水洗式以前の落とし込みトイレの隅に置いてあった落とし紙とか「ワラ半紙」のイメージですね。安いだけが取り得の我ら下級労働者ご用達のどーしょーもない紙。
ところが実際に印刷物に使用する再生紙のお値段はといえば、なんと原料のパルプ材から生産する新紙100%のものよりも高価なんだそーです。
いやぁ、知らなかったですねぇ。印刷屋さんに奉職していたにも関わらず、なんとも認識不足なオハナシでした。
ちょっと前まで「再生使用」表示というのは、「環境に配慮しています」というメッセージを「さりげなく」伝えているという気がしていたという印象を上の記事で載せていたのだけど、再生紙の方がコストがかかっているのならまったく違う。「さりげなく」なんぞではなくて、「コストを支払ってでも環境に配慮する」という意見広告のような、堂々とした主張なんですね。企業や団体が自らの理念を予算を組んで堂々と主張するのには異議ございません。はい。
というわけで、上掲記事は大幅に校正し再生利用させていただきました。だから、どことなく歯切れが悪い(^^;
しかし、再生紙が新紙よりも高価であるということも、なかなか腑に落ちない感じがする。
再生紙が高価になるのは、ゴミ不純物を除去し新紙と同じ純度にする手間がかかるからでしょう?だって例の「ワラ半紙」は白い紙に比べて格段に安かったもの。
なるほど、パルプ自体の消費量は押さえられると思うが、その他の中間媒体(触媒・燃料・人件費)の使用は却って増大しているという部分がどうしても引っかかりますね。もちろん、天然資源の保護が第一義なんだから、他の資源の使用のことは目をつむるというリクツですかね。
でもね、ある目的の為には他の項目を犠牲にしてもいいというリクツ自体が環境を破壊してきた元凶だったんではなないだろうか? 現在では資源・環境という呪文が異様に膨らんでファシズムを形成していくような不穏な気配を私は感じてしまうのだ。*2)
思うに再生紙を使用するなら、コストをかけずに、わらくず斑入りのままでもいいではないか?別にわざわざコストをかけてまで新紙のマネをする必要はないと思う。企業・団体が発行する印刷物が、再生紙を使用していても「新紙使用時代」と同じ紙質を維持しなければならない、という認識に無理があるのではないか? だから、せっかく「高価な」再生紙を使用しているのに、見かけは新紙と変わらないのでは困るじゃないか、ひとこと言っておかねば、ということにもなる。
広報誌や取り扱い説明書のように、愛蔵したり生涯読書を繰り返すような性格の印刷物ではないものなら、耐久性も高級感もそんなに必要ではない。紙質にこだわるのは、大量消費時代の美意識が未だに生きている証拠で、資源保護の精神はうわべだけのマネごとにすぎないということを如実に示している。
「ワラ半紙」のような浅黒い安くて実直な庶民労働者風の紙に印刷したとき、はじめて「用紙は再生紙を使用しています」というエクスキューズが本来の意味を持ち輝いてみえるのではないだろうか?
↑でも、そんな紙ならわざわざ言わなくとも一目でわかるというものだ。結局「再生紙を使用しています」という注意書きに対する違和感はいつまでもなくならない。
(02.3.3)
- 注記*2)
- 某企業のパンフレットは上質の新紙を使用しているが、それでも「再生紙使用」と表示させている。「再生紙使用」という呪文はすでにそこまで社会的圧力になっていた。ささいな偽善を容認していると、いつか確信犯的悪に成長していく。
(2002.2.1)
〜にやさしい
「地球にやさしい」
「環境にやさしい」
このコピーを最初に作った人はエライ。
大ヒットですよ、これは。
本来下積みで目立たなかった地球を擬人化し、ひょいと隣人のような身近な視点で扱った意外性が面白かったなぁ。
でも、この爆発的ヒットが追従されてコピーがコピーされていくうちにだんだん鼻についてきてしまう。要するに、もう新鮮な意外性はなくなっているのに、
せっせとお守りのように使いつづけているコピーのコピーしかできない人達が煩わしくなってきた。「何々にやさしい」という言い方もこれだけワンパターンで繰り返されれば、
発話者の語彙の貧困が露骨に感知されようというものだ。
もっと言えば「環境にやさしい」と唱えさえすれば、とにかくなんかいいことをしてるんだという表明になっているというコトバに対する甘えも見えてくる。社会のキーワードが「環境」に変わると、とたんに「環境」という語が蔓延するのもおそろしい。
「地球にやさしいお料理」
「環境にやさしい課」(大阪府池田市)
「環境にやさしいバスの紹介」(東京都営バス)
「環境にやさしい自動車の展示会」(運輸省)
なんだい、キミ達は?あんまり安直に他人の作ったコピーを流用して恥ずかしくないの?
もともと地球は人間じゃないので、自分で「やさしくしてくれ!」なんていうはずはない。
擬人化というのは立派な「ウソ」である。もともと人でないのに人のごとくいう、その「ウソ」の面白さを楽しむモノである。だから、最初面白かった「地球にやさしい」という言い方も、ここまで流通してくるとフィクションとしての面白さなんてもうとっくになくなっている。
「環境にやさしい」というのはもともと「ウソ」だということを、みんな忘れているんじゃないだろうか?
「環境にやさしい自動車」(運輸省)って、そんなものあるわけが無いでしょう?
運輸省の言っているのはせいぜい以前よりも排気ガスが抑えられ、消費燃料が少ない自動車のことのようである。
冗談じゃないよ、それって「以前よりも悪くはない」だけのことじゃない?マイナスが少ないというだけで、「やさしい」なんて言えるのかねぇ?
いかなる排気ガスも出さないことでマイナスがなくなって0になり、走れば走るほど空気を清浄化できて初めて「環境にやさしい」というんではないの?
でも、いくら排ガスをださなくとも、騒音や振動、交通事故はなくならないんでしょうから自動車が「環境にやさしい」なんて私には信じられませんね。まあ、せいぜい「環境をやさしく破壊する自動車」ってくらいの意味ではないか。
環境
「いたいよ。自動車でなぐらないでくださいよ!」
運輸省 「だからぁ、ちゃんと やさしく なぐってるだろ!」
ささいな偽善を容認していると、いつか確信犯的悪に成長していく。
(2002.2.1)
〜のホウ
「時間のホウを取りたいと思います。」
「両替のホウを行ってください。」
故あってナントカツアーという海外団体旅行に参加した。参加者の大半は現役を引退した老夫婦だった。諸費用も団体料金で安いし、自分で交通の手配をせず名所を観光できるので楽チンである。いよいよ当方も団体ツアー旅行適齢になったかと苦笑した。
しかし、何事も人任せで気楽な旅行にも、やはりメダルの裏側はある。
絶えず窓外の光景を説明してくれる30台女性現地ガイド嬢の口調が気になってしかたがない。
やたらと「〜ホウ」を連発するのである。
元来「〜の方」というのは複数のうちの一方を示す言い方だった。
例:「弟の方が頭が良い」
「兄よりも」という対立要素を意識させる。
もしくは「方向」の意味。
例:「向こうの方にあります。」
正確にどこと指定しているのでななくて、漠然と方向を示している。
だから、ぼくは「〜のホウ」といわれて、頭の中でどちらの意味だか考えてしまう。
「時間のホウをとりたいと思います」
「時間」以外にも採るものがあるのかな。いや、「時間をとる」のと「とらない」のと2通りあって、これは「時間をとる」ホウを採用するという意味だろう?
「ここで両替のホウを行ってください」
「両替」以外に何か選択肢があったかな。あ、「トイレ」ではなくて「両替」、ということを言外に言ってるのか!確かに、「トイレ」というと直截的だもんな。
「これよりホテルのホウへとまいります」
これはホテルの方角に行くという意味?いや、ホテルそのものに行くハズである。「ホテルに行く」と行ってしまうと、実際に事故でホテルに到着しなかったときに困るからか?「ホテルじゃなくて、ホテルの方」だと、とりあえずはホテルに着かなくともウソにはならないから?
「私のホウまでおっしゃってください。」
他にもいろいろ居るが、他でもない私の方に?しかし、ガイドさんは一人だよ?あ、とりあえず自分の居る方向に何か言ってくれれば、自分でなくとも他の誰かが聞いてくれて最終的には私に伝わりますよと?実際は一人だが、なんとなく「私以外の存在」をにおわすような?
「1971年に移転のホウを行いました」
うーん。移転以外にも「閉鎖」とかの選択肢があったのか?いや、「移転の方向」で事態は動いた・・・ええい!いいかげんにせい!
この辺で実は私の頭の中は切れている。我慢の限界である。そこで、周りの人に同意を求める。
「このガイドさん、〜のホウって、言いすぎてません?」
しかし、反応はこうなのだ。「別にぃ?普通じゃないの?」
。
やだなぁ。みなさん、違和感を持ってくださいよ!決して聞き流してはいけませんよ!
物事をボカしていうのは、営業上大事なテクニックかもしれない。というよりも、明確に物事を指し示さないのは、一種の顧客に対する丁寧語という意識が働いているんだと思う。しかし、はっきりいわねばならないものははっきりいってください。
「時間をとります」
「ホテルに向かいます」
「私におっしゃってください」
「移転を行いました」。
はっきり言っても絶対に失礼にはならない。大丈夫だよ。
この傾向は女性に強くて、移動先でガイドをしてくれた男性の口調では「〜のホウ」の乱発はそんなにひどくは無かった。
このまま女性の営業用口調として定着していくような予感があって困惑してしまう。
まだ、営業用だけだといいが、ふとこのような光景が頭に浮かぶのだ。
先生「では、これからテストのホウ、はじめますので、問題用紙のホウ配ってください。時間のホウは30分になります。何か質問のホウ、ありますか?」
補足)この他にも、この女性のボカシ言葉の使用例は多かった。
「〜ホウ」の頻度が一番として2番目以降を上げる。
#2 「〜か、と思います。」
「散策するのもいいか、と思います。」
「便利ではないか、と思います。」
#3 「〜となっております」
「人口は30万となっております。」
「お昼はサーモン丼となっております」
#4 「〜してみたいと思います」
「これから一路、ホテルのホウへと行ってみたい、と思います」
「見学のホウをしてみたい、と思います。」
(2004.3.9)
- <付記>
- 先日テレビで、モデルの仕事を斡旋するとだまし、若い女性から金を巻き上げる詐欺の手口が紹介されているのを見た。
私が懸念していた通りだった。
- この詐欺師の口調は「ホウ」のあいまい性を100パーセント利用していた。
-
- 「合格のホウがとれましたので、次はカメラリハーサルのホウになります。料金のホウは3万円になります。」
-
- 次の言い方と比べると、いかに上記のセリフが責任回避に満ちているかがわかるだろう。
-
-
「合格にしましたので、次はカメラリハーサルをします。料金は3万円です。」
(2007.1.17)
「まごころをこめる」
「心がつうじる」
なかなか日常的に使用するには、ちょっと気恥ずかしい美辞麗句である。
しかし、テレビのCFではいとも簡単に使用してらっしゃる。
某消費者金融のCF:
「私達は毎日、まごころ込めてティッシュをお渡ししています。」と言うセリフ。
ティッシュをもらった男がニコリと笑う。
「心が通じたとき、この仕事をして良かったと思います。」
ま、多少のコミュニケーションは成立したんでしょうよ。しかし、それが「心が通じる」と表現されたとき、当方は唖然としてしまう以外にない。
ティッシュを笑顔で配ってもらったら、私も喜んでいただいてますが、「まごころ」がこもっていたのかどうか知りませんし、別に「心が通じた」なんて思いません。単純にモノもらって得したな(^^)、と思うだけで。
もちろん、こういうCFは単なるビジネスを美しく表現し、企業イメージを上げる目的で作られているので、誇張があるのは承知している。とにかく、「我々はもうけたいんだよ。お金を出しなさい。」という本音だけ見せてもどうしようもないというものだ。
ここしばらく未曾有の経済的停滞がつづき、現に私メも失業してしまいましたが(^^;、各企業では必死に生き残ろうと、いろいろ手段を講じているようだ。よく聞く中には社員の「モチベーション」を上げる、というのがある。
つまり、仕事に積極的に取り組ませる、個人的な動機づけを行うのである。企業にとっては当然の手段だと思う。同じ給料支払うなら、もっと働いて欲しいと策謀するのは当然だ。
イヤイヤ働いてたのでは生産効率があがらない。だから、仕事というのは日々の糧をあがなうためにイヤイヤするものだ、という意識を捨てさせなければならない。仕事の目的はそんな卑小な個人的なものではない。もっと豊かで高尚で、社会の役に立つことなのだ、という意識を社員一人一人に持たすことが肝要ですね。
昔、某企業の工場で働いていたときには毎日必ず、社提を斉唱させられた。「ひとつ。産業報国の精神。」等々。(←どこか分かった?(^^))
しかし、こんな文言はラジオ体操と同じ、タダの気勢を上げる呪文で、意味なんて別に誰も考えてはいなかった。要は集団で行動するという条件付けができれば良かった。
しかし、最近の「モチベーションを上げる」というのは、もっと個人の内部に入り込んでくるまで指導されるようです。
しかし、どうして「金を稼ぐために働いてる」という素朴な理由ではモチベーションが上がらないというんだろうか?
「まごころが通じる」とか、「社会に貢献する」とか、なんでそんなに回りくどい動機付けをせねばいかんの?
金以外の目的が主だったら、慈善団体や親睦クラブ、あるいはNGO活動なんかに参加すればいいと思う。会社では「もっと働いたら給料があがる」だけが勤労意欲の源であったとして、いったいどこがいかんの?
ひょっとしたら、何か「金を稼ぐ」ことを前面に出すのは、ヤマしいという意識があるのかな?もちろん、金ではなくて、「仕事が好きだから」とか、「勉強になるから」だとか、個人的には労働にいろんな動機があっても良い。でも、それは正に個人的な動機であって、すべての同僚諸氏に共通するものではない。企業の中の労働者の共通の勤労動機としては「金を稼ぐ」為という正当かつ公正な理由だけが唯一の最大公約数として存在するだけだ。まして、企業の側が「利潤追求」あるいは「企業・社員の利益を守ること」以外の労働への動機付けを行うとしたら、それは入社した社員への労働契約不履行ということになるのではないか。
例を挙げて申し訳ないが、「産業報国」の社提の斉唱をさせることがこのような意味なら問題だ。「君達が働いているのは金のためではない。産業を通じてお国に報いているのである。だから、給料が上がらなくとも、もっともっと働くべきなのだ。」
おいおい。会社自体はそのような高邁な精神に基づいて設立・運営されているのかも知れませんが、私は単に「この労働でこの給料」というだけの契約で就職したのである。そのような「報国」が条件だとは一切聞かされてませんでしたよ?
(お断りしときますが、これはあくまで例示のための虚構です。この社提を持つ企業での実際の勤労体験ではありません。念のため。)
企業があまり美辞麗句にこだわると、どうも私は茶化したくなってしまう。ごめんなさい。
でも、小声でぶつぶつ。
ささいな偽善を容認していると、いつか確信犯的悪に成長していく。
付録)「まごころ」云々以外にも、どうも消費者金融系企業のCFには抵抗がある。
その1)
妙齢の女性が愛想のよい笑顔で愛嬌をふりまく。要するに、しきりと「金を借りにこい」と勧誘してくれるだけなんだけど。多分歯並びが理由でCFの主役に抜擢されたこの女性タレントは、30秒間ずっと固定した笑顔で通し、それがまるで顔に張り付いたとしか見えないのである。
もちろん、「もっと気楽に消費者金融を利用してください」というメッセージを体現しているのであるが、ぼくの感覚ではやはり「金を借りる」のは絶対に気楽ではない。どうしょうもなく、困り果てた末に門をたたくのだ。昔の質屋は堂々と入るところではなかった。質屋の方も派手な宣伝などはしなかったものだ。だから、女性の笑顔に誘われて、なんて、そんな単純な理由で金を借りに行くとは思えない。質屋の親父は閻魔様のような顔をして「きちっと返済しなきゃ、質草流してしまうぞ」という警告をするのが正しいと思う。
このCFの女性は満面の笑顔で「金を借りてくれ」というが、それは企業の真の目的ではない。「返済に伴う金利を支払え」というのがこの企業の利潤の源であり、企業活動の目的だからだ。しかし、その真の目的は、この女性の笑顔が覆ってしまってまったく見えない。笑顔が完璧であればあるだけ、金を借りるというのはそんな簡単なコトではないぞ、という警告がぼくの内部に発生し、女性の笑顔がいつしか「金利支払え」という閻魔サマの醜怪な顔とダブって見えてくるのだ。
その2)
以前「がんばる」という言葉の無目的的用法が気になると書いた。
その意味でもテレビで放映されていたこの消費者金融企業の、別のCFのセリフが引っかかっていた。
「わたし達はティッシュ配りでがんばってます。あなた達は踊りでがんばってください!」とティッシュ配りのお姉さんが、ダンサー達を激励するヤツである。
この会社はがんばってるのだ。その後顧客の盗聴を指示したとしてこの会社の会長が逮捕された。そして、便乗でもなかろうが、元社員が役員に人権を傷つけられたとして告発もしている。ニュースで報道された、役員の社員への叱責の録音の罵倒のありさまは、この会社の体質を体現していると思われた。
会長も役員さんたちも「がんばって」るのだ、この会社は。まあ、無目的的にがんばってるワケではないんだろうけど。
(2004.3.9)
ふれあい
「ふれあい広場」
「ふれあい公園」
「広報誌ふれあい」
「ふれあいセンター」
・・・・・・・等々
この秋はバイクで郊外を走り回って過ごしていたが、「ふれあい」という文字がやたらと目につくことが気になりはじめた。比較的最近に設立された地方の市町村立の公共施設の名称に使用されているケースが多く、したがって道路走行中の目印にすることも多い。
「ふれあい」という文字の印象はやさしく、あたたかい語感があり、「ひとびとの交流」というような語義も感じさせるので、地方自治体が設立する公民館のような集会場にはふさわしい名称なのかもしれない。しかしここまであふれかえってくると、この命名の発議者の精神の安直さに思い至り不気味な気配が私をおののかせ始める。どうやら「環境(地球)にやさしい」の次のワンパターンキーワードは「ふれあい」のようである。
「心のふれあい」というような言い方が先ずあったと思う。これはかなり気味わるい言葉である(^^;
何かこちらのプライバシーに土足で踏み込まれ、「何の権利があって?」と抗議すると「わたしの方のも見せたげるからさぁ、いいじゃん?」とか強引にせまられたり。う、きもちわるぅ。
で、「ふれあい」だけだと「心の」が抜けてるので、当初さほど『気持ちわるーい』印象はなかったのだが。
よく考えてみると「ふれあい」って「さわりあい」のことでしょう?「触れ合い!」 二人であるいは大勢が集まってべたべた触りあう。で、ここで触られて少し行くとまた向こうでも触りに来る。このイメージを胚胎してしまうと、「ふれあい何とか」の氾濫は、ちょっと私には耐えられなくなってくる。
ただ走り抜けたいだけなのに、ふと気が付くと道が「ふれあいロード」に変身して待ち構えているのだ。すいません!ただの通りがかりです、見逃してください!
「ふれあい牧場」 動物に触れられます。あ、その通りじゃないか!
でも、それって何か「ふれあい」ちがいのような気も?動物の方は別に触られたくはないと思っているのかも知れないのでは?
このことば当然ながらというか、高齢者向け施設にも多く冠せられ、「ふれあいの里」「老人ふれあいの家」などと、かなりの目撃例がある。ここで明らかなのが「孤独な老人」というイメージである。「ふれあい」にはすでに介護というキーワードさえも含んでいるイメージとしての度量の広さがある。うむ。要するにこれからの高齢者化社会を見据えた、かなり有効なキーワードとなりうるのだ。それはそれで結構なんだけど、私がいつも気にいらないのは、キーワードが確定してしまうと必ず安直なコピーが氾濫し、それさえ唱えていれば他のことなどどうでもいい、というような風潮になっていくのが見えることだ。
老人は孤独で常に他人との交流を望んでいる? そうかもしれない。しかしそうでない老人もいるかもしれない。
私は見知らぬ他人から「そこのおとうさん!」と呼ばれたくないし、ましてあかの他人に「おじいちゃん!」と呼ばれたくはない。
老人になり果てたら、せいぜい他人の迷惑にならないよう気をつけるつもりではある。経済的な支援や介護はありがたく頂戴しますが、それでも「ふれあい」よりも「自立」を旨としていきたいのである。と、ちょっと気色ばって思ってしまうのは、「ふれあい」ということばの不気味な増殖から、「老人の個人としての
尊厳」が考慮されなくなっていくような不穏な気配を感じてしまうのである。
私はここで「ふれあい」ということばにこだわっているのではない。それを安直に繰り返す精神のことを言っているのだ。
個人と集団とのかかわり合い方はさまざまで、今まで私はどうにかそれなりに苦労して社会の中での自分の適正な位置を模索してきた。
老人になったとしても個人であり続けることには変わりない。
人は「孤独な老人一般」というものになるのではなく、個々の老人になるだけなのだ。
単純なキーワードを繰り返して事なれりという精神は、たやすく言葉による暴力を受け入れてしまう。
「最初にことばありき」とファシズムは言った。
(2007.1.17)
・・・のかな?と思う。
解散総選挙の可能性もあるのかな?と思う。(政治家)
これが原因なのではないのかな?と考えられる。(大学教授)
販路が拡大していけばいいのかな?と考えています。(経営者)
活性化につながればいいのかな?と。(地方自治体職員)
環境にいいのかな?と。(一見サラリーマン風)
近頃テレビ報道番組で見る限り、急速にこのふやけたボカシ言葉の侵略が進んでいる。
最近の日本語表現に顕著な、断定を避ける心理が選択させる婉曲法ですね。理屈は判っているのだが。
幸いウチの地方の方言では、こういうヘンに小上品な東京の学生口調をはさむことが出来ないので、日常生活では遭遇したことはない。
こいつの実にイカんところは、テレビニュースでよく目撃するように、政治家や経営者、自治体の職員、教員等の公(おおやけ)の発言内で多用されているところにある。
「・・かな?」は自問の独り言で、決して公的に言えるようなモンじゃないぞ。
断定を避けたければ「という可能性もある」「かも知れない」というレベルにとどめるのが公式常識で、話者の自問をくちゃくちゃ聞きたくはない。「可能性もあるのかな?と」「かも知れないのかな?と」に至ってはぐちゃぐちゃにくねってしまって、聞かされるコチラが悲しいぞ。
多分、最初に公にこの表現を使用した方は、私的な「・・なのかな?」を入れることで公式発言風の固さを和らげる効果を意識したのだと思える。
しかし、このように蔓延してしまっては最早やわらげ効果はとっくに失効、はやり文句を繰り返すだけという言語感覚のニブさしか私には感じられない。
「見守る必要があるのかな?と思いますね」(NHKニュースウォッチ9時のキャスター大越建介氏)
こんなニブい人達が大勢出てくる国のニュース報道を見ている私はつらいのだ。
解散総選挙の可能性もあると思う。
これが原因ではないかと考えられる。
販路が拡大していけばいいと考ています。
活性化につながればよいと考えます。
環境にいいと思います。
と、どうして普通に言えないんだろうか?
(2010.4.13)
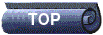
.jpg) (京都 南禅寺山内掲示)
(京都 南禅寺山内掲示)