 ドイツ語クラスにて(2) ドイツ語クラスにて(2) |
|
ハイデガーと大島淑子 (2)  |
〔フライブルグ通信〕
ハイデガーと大島淑子 (1)
2012/09/14
 何とか持ち帰った一連のハイデガー関連の文献を整理し、またすくなくともイエナで購入した「SEIN UND ZEIT」を読んでから書き始めようと思っていたのだが、すでに帰国してから一年たっぷり経てしまった。
何とか持ち帰った一連のハイデガー関連の文献を整理し、またすくなくともイエナで購入した「SEIN UND ZEIT」を読んでから書き始めようと思っていたのだが、すでに帰国してから一年たっぷり経てしまった。ハイデガーに取り組むどころか、フライブルグの記憶そのものまで風化してしてくる始末。 うむ、案の定だなぁ・・・
もういい加減にブログの連載をクローズしなきゃ、HPへの移動もできない。
だから、あまり「哲学的に」気負わないで旅行記としての内容で簡単にまとめることにする。
しかし、やはり「存在の不安」に関しての言及から始めなければ始まらない。
当初から「存在の不安」というキーワードが私をフライブルグに導いたのだったから。
フライブルグ大学の夏季ドイツ語講座に参加する経緯については、ブログの「フライブルグ通信」ではなく、「欝へのご招待」書庫にいれた「外に自閉する 2」に詳しく書いた。
つまりは外の東日本大震災と呼応して、私の内側に顕在化してきた鬱の気配が先ずあった。
ここで「気配」と書くが、これは既に私の中ではアレが始まっていたからなのに他ならない。
三輪与志の「気配」。 (埴谷雄高「死霊」 全集現代文学の発見「存在の探求」所載 1976)
いきなり核心に踏み込むが、私の存在論哲学の核は埴谷雄高が思春期の私に植えつけたものである。
だから哲学ではない。明らかに文学由来の存在論なのである。
いや、もっと言えば哲学だけではなく、私の文学そのものさえこの地点から出発しているのである。
「私の文学」なんて書いてしまうと、まるで自分が一端の文学者のようではないか、と笑うヤツは必ずいる。
だから「私の文学への関心」というように訂正するというバカバカしい調整的配慮も必要になる。
しかし、「私の文学」でいいのだ。少しも間違っていない。
あやつらは職業や金・地位というものしか見ることができない輩である。
しかし、私がここまで生きてこれたのは、私が就業してきた職業によってではなく、間違いなく私の文学に負っていたのだ。
でも、金のためにも生きねばならない。
現役時代の私の問題は「世界との折り合いのつけ方」だった。
世間や時代と私の精神が折り合わず、どちらかというと「群集の中の孤独」(オルテガ)が問題だったといえる。
現役を退き、もうばかばかしい演技までして世間と折り合いをつける必要がなくなった。
私に残された手持ちの時間はもう私の好きに使っていいのだ。
事実、通常の定年より早く会社社会を抜け出した私には「黄金の10年間」(堺屋太一)が待っていたと言える。
しかし、それでもアレはやってくる。
三輪与志の「気配」。
会社や学校という外の社会との摩擦の問題ではない。
自分の内に巣食っている、どうしても確定できない、言い切ることのできない、不安。
遂に世界に自分ひとりとなったときでも、やはり私には確信ができず、決然と生きることができない。
世界とは何か
自分とは何か
存在とは何か
自分とは何か
存在とは何か
「存在の不安」というコトバがそのような感覚を言いあらわしていると、17歳の私は感じたのだ。
そして、その時から私は言葉によって自分を記述し、見極め、定義しようとしてきたのである。
実社会から抜け出してしまった私は、負担のないように社会と自分との距離を自由に調整出来るようになった。
しかし、その地点からでも東日本大震災に呼応し、17歳の自分が抱いた不安の根源が相変わらずソコに居座ったままなのを見つけてしまったのだ。
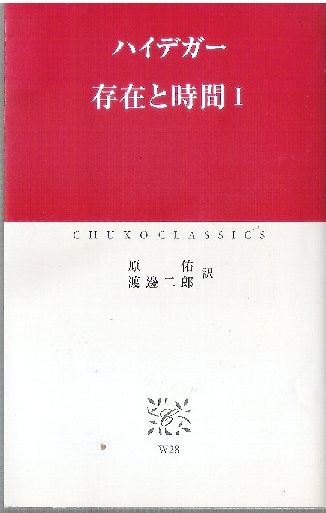 ---
---
フライブルグに行き、ハイデガーを読む。
外に自閉する。
外に逃げ出し、内に沈潜する。
そのように決定してから、実はまた外との面妖なやりとりが続いた。「外に自閉する(2)」参照。
ここで最期にフライブルグ大学言語研究所のNothen部長からE-メールが来て、最終的にフラ大に受け入れてもらえることになった。
この人が夏季語学講座の責任者で、哲学者大島淑子氏の友人でもあったことが、その後の思わぬ展開に拡がっていく。
日独友好150周年という節目だった。
この旅行の最終日でも、ベルリン当局が私の滞在にあわせブランデンブルグ門での式典を挙行し、歓迎してくれたのだ。
 フライブルグ大学滞在2日目にNothen部長から日独友好150周年記念講演会への案内がメールで届いた。
フライブルグ大学滞在2日目にNothen部長から日独友好150周年記念講演会への案内がメールで届いた。
これは講座に登録している日本人全体への招待状だったが、それによって私は大島淑子氏の「ドイツ語を学ことは、すでに西洋哲学の道をあるいていること」と題された日本人受講者への記念講演に引き寄せられる。
大島はそこで自伝的にハイデガーにアプローチするきっかけとなった日々のことを語り、フライブルグに参集した若者を激励する。
大島はそこで自伝的にハイデガーにアプローチするきっかけとなった日々のことを語り、フライブルグに参集した若者を激励する。
大島の語る若い日々の苦悩は、いわば真摯に生きようとする若者なら一度は陥る普遍的な蹉跌といえよう。
そして、ある種の倫理的潔癖さを自分に課してしまうような性向を持つ魂だけが「自分とは何か?」という根源的な懐疑に陥っていく。
そして、ある種の倫理的潔癖さを自分に課してしまうような性向を持つ魂だけが「自分とは何か?」という根源的な懐疑に陥っていく。
大島はそのような躓きの石を経てハイデガーの存在論にとりつかれ、そして規模ははるかに卑小ながら、私の側にもそのような経緯が。
私は何事か名指すことができなかったが、私がフライブルグに導かれてしまった内的必然性をこのとき教示され、ここに私と共通の言葉で語られる世界があると感じた。
私は何のためにここに来たのかを理解した。予定調和的高揚。
私は何のためにここに来たのかを理解した。予定調和的高揚。
この間の経緯も再説しないが、当初のフライブルグに抱いた誤算感を見事に払拭し、改めてハイデガーのフライブルグ大に来たのだ、という実感を抱かせてくれた。
また、そのころドイツ語を再び学習し、動詞としてのSEINの用法に内在する文法的な違和感を持っていた。
そして、それが「自同律の不快」(埴谷雄高)というテーマに回帰していく、という内的な結線回路を作ろうとしていた。
「私は私である」というとき、動詞としてのSEINの曖昧さが一気に存在そのものの不安定さを際だたせる。
広く言えば、フランス語を経てドイツ語を見ることで再びドイツ哲学の思考法の源泉を捉え得るとも思えたのだ。
大島の講義は正にこのSEINを使用する第二文型の問題から開始し、アリストテレス論理学の用語である同一律への懐疑へと導入していった。
それでは一体、このSEINは何を意味しているのだろうか?
「存在とは何か」
ここから大島の個人としての存在論へのアプローチがあり、禅を介する独自の展開に繋がっていく。
しかし、この筋道をここで解説するにはあまりに場違いだろう。
しかし大島のハイデガーの存在論へのアプローチは、私ど同様「文学的」であったことを指摘しておきたい。
哲学を大きく二つに分けても良い。
科学としての哲学 ・・ 「世界とは何か」 ・・ 現象学・論理学
文学としての哲学 ・・ 「自分とは何か」 ・・ 倫理学・宗教
私は大島のハイデガーへのアプローチが自分と同じ方向をむいていたことを知り、深く同意できた。
アカデミズムとは全く無縁な場所で私が考えていた存在論への切り口は、大筋では何も外してはいなかったのだ。
大島氏も独自に思想を展開していき、決してアカデミズムの本流とは言えないのだが、少なくとも問題意識を共有し、さらに深く考究していく学への道があるのだ、と私を啓発してくれた。
私は学において孤独ではない。
私はこのためにフライブルグ大に来たのだ、とここにして理解できたのだ。
私がフライブルグと決め、フライブルグが私を選んだのである。
 ドイツ語クラスにて(2) ドイツ語クラスにて(2) |
blog upload: 2012/9/14(金) 午後 7:04 | ハイデガーと大島淑子 (2) > |